今回は新リース会計基準における、借手のリース期間に関する考察をしていきます。
新リース会計基準では借手のリース期間算定において、延長または解約が「合理的に確実である」期間を含めることを求めています。
この「合理的に確実である」かどうかの判断が大変難しく、考察のポイントになってくる箇所です。
考察にあたって、まずは基準上での表記を改めて確認します。
以下、企業会計基準第34号_リースに関する会計基準第31項より
引用元:https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_02.pdf
31.借手は、借手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、次の(1)及び(2)の両方の期間を加えて決定する(適用指針[設例 8-1]から[設例 8-5])。
(1) 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(2)借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
上記について、企業会計基準適用指針第33号_リースに関する会計基準の適用指針第17項にて、補足がなされています。
引用元:https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf
17.借手は、借手が延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮する([設例 8-2]から[設例 8-5])。これには、例えば、次の要因が含まれる。
(1)延長オプション又は解約オプションの対象期間に係る契約条件(リース料、違約金、残価保証、購入オプションなど)
(2)大幅な賃借設備の改良の有無
(3)リースの解約に関連して生じるコスト
(4)企業の事業内容に照らした原資産の重要性
(5)延長オプション又は解約オプションの行使条
正直、上記の基準を一読しただけでは実際に借手リース期間の判定をどのようにすればいいのか、イメージが掴みづらいです。
そこで、リースに関する会計基準の適用指針ではいくつか設例を記載してくれています。
設例:https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04_01.pdf
(借手リース期間に関する設例は、上記引用元の[設例 8]〜[設例 8-4])
普通借地契約を代表例に、何パターンか具体例が記載されています。
実務では、これらの設例を参考材料にリース期間の判断をしていくことになります。
次章で各設例でのポイントをまとめていますので、詳細を確認したい方はそちらをご覧ください。
新リース会計基準_借手リース期間の考察(第2章)

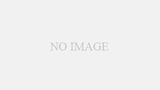
コメント