第1章では、新リース会計基準のリース期間に関する基準の概要説明を行いました。
第2章では、新リース会計基準実務指針に記載の設例について、ポイントを要約して解説します。
リースに関する会計基準適用指針の設例は以下です。
設例:https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04_01.pdf
(借手リース期間に関する具体的な設例は、上記引用元の[設例 8-2]〜[設例 8-4])
設例8-2の要点
①借手は事業用の店舗確保のため、貸手から建物内店舗用スペースを借りる契約を締結した。
②契約期間は1年であり、契約により最初の1年間は解約ができないと定められているため、解約不能期間は1年
(=リース期間は必ず1年以上となる)
③1年経過後も契約更新が可能で、更新にあたっての条件等は設定されていない
(=借手に延長オプションがあり、リース期間の算定にあたって延長オプション行使が合理的に確実かどうかを判断する必要がある)
④借手はリース物件に耐用年数10年の建物附属設備を設置しており、この附属設備は5年程度でメンテナンスが必要になる。
⑤当該店舗は借り手の経営戦略的に重要な店舗ではなく、損益状況によっては撤退も考えている
→上記を踏まえ、借手は耐用年数10年の建物附属設備を設置していることから、しばらくは当該店舗用スペースを借り続ける意思があると考えられる。
5年でメンテナンス、10年で設備の耐用年数を迎えるため、合理的に確実な延長オプションは5年か10年かの2択になる。
ここで⑤の重要な店舗ではない、という条件が判断材料となる。
重要店舗でないため、5年経過時点でメンテナンス費用を負担してまで事業を存続させるかは不透明な要素が多いと判断できる。
よって10年よりも5年の方が延長オプションを行使する可能性が合理的に確実と判断する。
設例8-3の要点
①から④の条件は設例8-2と同様。
⑤当該店舗は借り手の事業戦略的に重要な店舗であり、損益状況のみで撤退の判断を行わない。
→設例8-2との相違は、店舗が自社の経営戦略上重要か否かという点である。
設例8-3では店舗が経営戦略上重要であるため、合理的に確実な延長オプションは5年か10年か、10年以降も延長するかの3択になる。
ここで、重要な店舗ということは耐用年数10年の建物附属設備の除却に相当な費用がかかることが想定される。よって設例8-2と異なり5年で早々に撤退する可能性は低いと考えられる。
とはいえ重要な店舗といえど10年を超えて運営を継続するか、という点に関しては10年先の経営環境の見通しが難しいため、合理的に確実とは言い切れない。
よって3つの選択肢の中で10年が合理的に確実な延長オプションの期間と考えられる。
設例8-4の要点
①借手は事業用の店舗確保のため、貸手から店舗用土地を借りる契約を締結した。
②契約期間は40年であり、契約により最初の6ヶ月は解約ができないと定められているため、解約不能期間は6ヶ月
(=リース期間は必ず6ヶ月以上となる)
③借手は借りた土地の上に耐用年数20年の建物を建設する。当該建物は20年後に建て替えが可能であるが、建物建設時と同程度の費用が必要となる。建て替えの計画は今後検討予定である。
なお、借手の賃借期間に関する過去実績は、平均して25年間である。
④借手の事業計画では、この建物を使用して10年以上継続して事業を行うことが予定されている。
⑤当該店舗は借り手の経営戦略的に重要な店舗ではなく、立地が良い繁華街に面しているため、損益状況によっては建物の耐用年数に達するまで転貸を実施する可能性がある。
→②の記載より、借手は6ヶ月に告知することで解約オプションを行使できると考えられる。
そのため解約オプションの行使が合理的に確実か否かを判断する必要がある。
借りた土地の上に借手が建設した建物の耐用年数は20年のため、判断の選択肢としては20年経過まで解約オプションを行使しないか、20年を超えて解約オプションを行使せずに契約を継続するかの2択になる。
20年経過前に解約すると建物の解体費用がかかること、⑤により転貸でも収益を得られることから、20年経過まで解約オプションを行使しないことに関しては、合理的に確実と判断される。
一方で、③のとおり20年経過後に建て替えコストが発生することから、20年を超えて解約オプションを行使しないことについては、合理的に確実とは言い切れない。
よって2つの選択肢の中で20年が合理的に確実な解約オプションの期間と考えられる。
設例8-5の要点
①借手はオフィスとして利用するための建物を借りる契約を締結した。
②契約期間は5年であり、契約により5年間の途中での解約ができないと定められているため、解約不能期間は5年(=リース期間は必ず5年以上となる)
③5年経過後も契約更新が可能で、更新にあたっての条件等は設定されていない
(=借手に延長オプションがあり、リース期間の算定にあたって延長オプション行使が合理的に確実かどうかを判断する必要がある)
④借手は当該オフィスに重要な建物附属設備の設置を行わない。
⑤当該オフィスは借手にとって好立地であるが、代替の場所を探すことは容易。
なお、借手は過去に他のオフィスを10年間借りていた実績がある。
→②に記載のとおり、最低限5年間は当該建物を借りることになる。
借手に延長オプションがあるため、5年を超えてこの建物を賃借するかが検討事項となるが、④⑤の条件のように、借手側として当契約を延長することに対しての経済的インセンティブが存在しない。
よって、借手は延長オプションを行使しない可能性が合理的に確実より低く、リース期間は5年と考えられる。

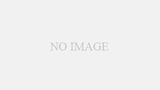
コメント